子供の持ち物が多いです。
たとえば、私が昔作ったおままごとのフェルト食材でボロボロになってるやつ。
もう要らなくない?というやつも絶対に処分しないという。
学習用具等の必要な物ではなく、使ってないおもちゃや工作の素材等々。
親が勝手に捨てたくないかつ自分で考えてもらう癖をつけたいので、失敗を積みながらちょっとずつ成長してもらえる方向にシフトしました。
なぜなら、子供の「全部取っておきたい!」気持ちを尊重しつつ私が収納を延々と模索する日々に疲れたからです。
もうこれ以上物を増やすのは子供、収納のために知恵を絞るのは親という状況を続けるのがキツイ。
私が子供の収納に手と口を出しすぎないようにして、小学3年生の今、自分で「もう要らない」と判断することがポツポツ出てきました。
今現在の子どもの持ち物の収納場所
子どものおもちゃ関連、そんなに買ってもいないはずなのに、貰ったり作ったりでコツコツじわじわ増えていく。
出しっぱなし収納やらなんやらと色々と試行錯誤を重ね、今は以下の収納場所に収めています。
- 100体以上のぬいぐるみを入れているカゴ
- 押し入れ下段全部&上段の半分←収納のメインでおもちゃがいっぱい
- 子供服クローゼットの空いている部分(宝物やオシャレを集約)
- ままごとキッチンの中(お皿やら食材やら)
- リビングに出しっぱなしにしているワゴン(工作系を集約)
- 本棚
- 工作品を入れておく大きな箱
- 無印の壁に着ける大きな収納棚×2(お気に入りのディスプレイ用)
これ以上場所は確保できないと本人も分かってはいるようで、上記に入る量だけというのは納得してもらうしかない。
我が家は狭い1LDK。これ以上収納は用意出来ないのです。
親が子供の物を「収納」するのを辞めた
以前は物が増えるたびに私が必死で頭をひねって「収納」していました。
新たに収納グッズを買い、取り出しやすいように工夫し、増え続ける減る気配のない物を頑張ってきれいに収めていた。
汚す人と掃除する人が別だと、「汚さないように」という意識は芽生えにくい。
それと同様に、どれだけ物が増えても私が工夫して納めてしまえば、物の総量や自分で管理できる量なんて考えるわけがない。
だから私が一人で必死で「収納」するのを辞めました。
(子供の片づけのお手伝いはしますが、あくまでお手伝い。)
子どもの持ち物に関しては「処分したくないなら取っておいていい」ルール。
ただし、収納に入る量まで。
ぐちゃぐちゃに押し込んであっても、そこに入っていればOKです。
そして、使ったら必ず元の場所に戻す。
次に使う時に困るのは自分。使いたいものが見つからなくて困るのも自分。
お友達に見られて恥ずかしいのも自分。
戻さなくて困るのも自分。
出しにくいしまいにくいということは、片づけ方の根本を変えた方が良いor物の量を減らすしかないのだと、私たち大人は知っています。
でも子供は知らないのです。
だから、言葉でも伝えつつ経験もしてもらう方がいい。
物を詰め込んだ結果どうなるのか。
どうやって並べたら使いやすいのか。
ぬいぐるみは一体も捨てたくないといい、結構な大きさのカゴ×2個にバランスゲームのように山積みになっている。
お目当てのぬいぐるみは取り出しにくくて、よく雪崩も起こしている。
今はそれでいいのだと、大人の私は割り切っています。
「最近急速に興味を失ってきたポケモンのぬいぐるみ、もう要らないかも」
「そしたら他のぬいぐるみが遊びやすい」
と思いつつ踏ん切りがつかないようなので、相談の結果ポケモンを目につかない場所に移してそのまま処分するかどうか試している最中です。
たまっていく子供の工作の作品について
絵はファイルに入れて保管できるからそこまで場所を取らない。
かさばるのは、立体的な大作たち(学校で作ってくるみたいなやつ)。
工作で作った品々も、もちろん出来立ての綺麗な状態の写真は撮るけど実物もとっておきたいらしいので、大きな箱にひとまとめに入れています。
普段、箱は押し入れ天袋に収納。
気に入ったものはディスプレイ。
「捨てたくない」という気持ちはよくわかる。
工夫して頑張って作った工作を、いくら写真を撮ったとはいえすぐ捨てられたら私でも嫌だ。
布からこだわって頑張って作ったぬいぐるみをすぐ親に捨てられるような気持ちを想像してみる。
ミニマリストの方の本を見ると、飾ることなく写真を撮ってすぐ処分している人が多い印象。
子どもさんはよく反発しないなぁと思う。
私は子供時代にそうやってすぐ処分されてて悲しかったんだけど、そのうち諦めて悲しさを感じなくなっていったから、それを本の中の子供に重ねてしまう。
箱に入れた作品はたまに見返しつつ、奥の作品から押しつぶされていってます。
そうやってつぶれたりは本人的に惜しくないらしく、旬が過ぎると「もう要らない」と言うことがある。
箱にある作品たちで季節性のあるやつはインテリアにもする。
置き場もないので天井からぶら下げて、エアコンの風に揺られています。
最近、3歳ころに作った紙コップのお雛様を処分しました。
飾ったり眺めた時に、去年までは嬉しかったのに何も心が躍らなかったそうです。
「今の方がもっと上手に作れるし飽きた」そうです。
ミニマリスト本や収納本で読んだ内容を子供に共有する
「この家、うちと同じような広さ・間取りで、こんな風に収納しているんだって」
みたいに見せる。
ランドセル以外の子どもの物が、洋服を含め本棚の1段分しかない家を見た時はビックリしていました。
逆に、雑誌には広くてお洒落な子供部屋が載ってたりして、一緒に羨ましがっています。
スペースが許すなら、天井からブランコが下がった部屋に子供用ティノピーを立て、滑り台や雲梯も置き、イケアのキャンパス置きみたいなお絵描きアイテムを置いて、おもちゃいっぱいの走り回れる子供部屋があればなぁ。

最近子供にヒットしたのは、タイトルを失念したミニマリスト本に書いてあった「まぁまぁは要らない」的な言葉。
- まぁまぁ似合うけどすごく似合うわけではない服=似合わないから処分する
- まぁまぁ必要(あれば使う)けどすごく必要ではない=不要
みたいに、「まぁまぁ」とか「どっちでもいい」なら要らないんじゃない?的な考え方。
この考え方にいたく納得したようで、片付け時に迷ったときの指針の一つとなっているみたい。
小さい頃におままごと用に作った飲食店のポイントカードや、昔好きだったキャラクターのシール。
成長した今は「あってもなくてもいい」、だから「要らない」と持ってきた。
「色んな考え方の人がいるんだなあ」の中から自分に合う考えかたを実践してみたらいいと思います。
「出しっぱなしでOK」のミニ机を設ける
何日か連続でやりたい遊びってありません?
時間のかかる手芸、難しいパズル、レゴ。
今までも出しっぱなしOKテーブル(自由に使っていい自分専用テーブル)を置いていたのに、全く使わず食卓を使うので、必ず片づけてもらわないといけなかった。。
家具のレイアウトを変えたら使ってくれるように。
(部屋の隅から部屋のど真ん中=目につく場所に移した。)
丸1日経過しても触らないでただ出してあるだけ状態になった時は、声をかけていったん片付け。
遊びは思う存分やってほしい。
ルールは厳格でなくてもよいと思うことにした
「出したものは自分で元に戻す」
「夜ご飯までに出したものをリセットする」
「収納に入る分まで」
「飾りたい物たちの管理(ホコリ拭き)は自分でやる」
といったルールを設けてはいますが、厳守は目指していません。
学校から帰って、見るからに疲れている日があったり。
ついつい遊びに夢中でレゴを散らかしたまま夜ご飯の時間を迎えてしまったり。
そういう時は子供:親=2:8くらいで片づける。
そういう日は誰にでもあるから、1割でも自分で動いて片づけてくれればいい。
「お母さん手伝ってくれて優しい!ありがとう!」と感謝してくるのが可愛いです。
以前は私がやって当然だったから。
昔は「どんなルールでも例外があった方が子供が迷う」と思っていました。
でも外で頑張っているのだから、家で出来ない日があるくらい良いに決まってる。
何度も失敗をくりかえしたらいい
子どもが最近言っていたことで印象に残った言葉がある。
「自分一人でやるようになったことは、最初はお母さんとやるより失敗が増える。」
図書館で本を借りる時に「借ります」を「返します」と言ってしまったとか、そういう小さい失敗が増えるそうです。
子供時代の特権は、どれだけ失敗しても親がリカバリーできるということ。
だからたくさん失敗したらいい。
(もちろん失敗を望んでいるわけではありません。)
私も余裕がないと子供の失敗にイライラしてしまうけど、失敗から学ぶものは本来貴重なものであるはずです。
大人だって、同じものを2個買ってしまったり、賞味期限を切らしてしまったりとかあるんだし。
「あれがない!」
「ここに置いたはずなのに」
「さっきまであったのに、雑に放り込んだから入らない!」
「飾りたいものを無限には飾れない!」
そういうことを体験した先に、自分で物を管理できるようになる未来が待っていると信じて、のんびり一緒に子供の片づけをフォローしていきたいです。



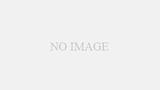

コメント